「歯ぐきから血が出る…」それ、歯槽膿漏のサインかも?歯医者でできる治療法を解説|お口の健康コラム|土日祝診療、キッズスペース・駐車場完備、船橋のあおぞら歯科クリニック本院

あおぞら歯科クリニック本院
AOZORA DENTAL CLINIC厚生労働省認定 口腔管理体制強化型歯科診療所
歯科外来診療環境体制認定施設
047-422-7177
【平日】8:30-19:00 【土日祝日】8:30-15:30
Column お口の健康コラム
歯の知識
「歯ぐきから血が出る…」それ、歯槽膿漏のサインかも?歯医者でできる治療法を解説
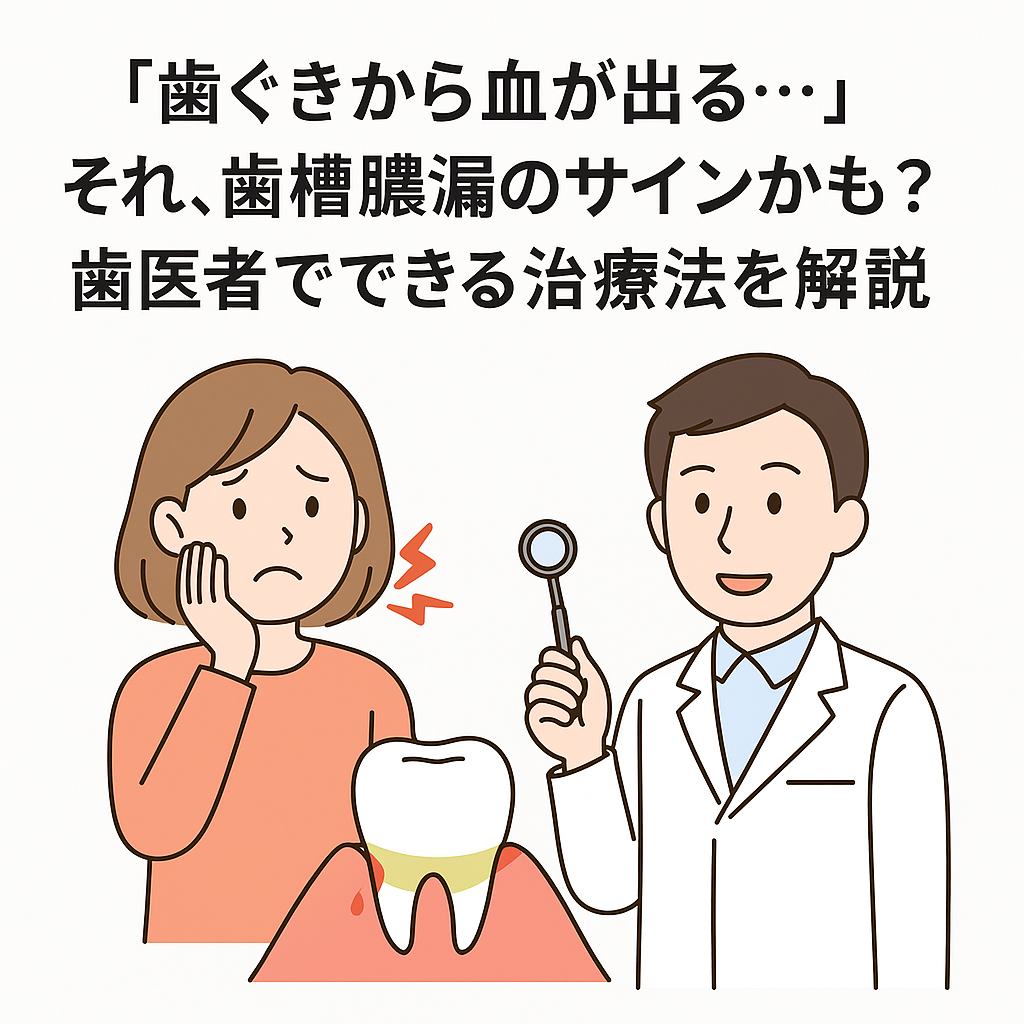
親子三代で安心して通える歯医者、船橋市のあおぞら歯科クリニック本院です。
皆さん、「歯ぐきから血が出る」という経験はありませんか?実はその症状、歯槽膿漏(しそうのうろう)のサインかもしれません。歯槽膿漏は、歯を支える骨や歯ぐきが炎症を起こし、放っておくと歯がぐらついたり抜けてしまう怖い病気です。当院にも「痛みはないけれど歯ぐきから血が出る」と相談に来られる患者様が多くいらっしゃいます。早期に治療を始めれば進行を止めることができ、健康な口元を取り戻すことが可能です。今回は、歯ぐきの出血と歯槽膿漏の関係、そして歯医者での治療法についてわかりやすく解説します。この記事が皆様の参考になれば幸いです。
歯ぐきから血が出るのはなぜ?歯槽膿漏のサインを見逃さないために
歯みがきをしているときや、リンゴをかじったときに歯ぐきから血がにじむ――。そんな経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか。
一見、ブラッシングの強さや一時的な刺激が原因のように思えるかもしれませんが、実はそれが**歯槽膿漏(しそうのうろう)**の初期症状であることも少なくありません。歯槽膿漏は、歯ぐきや歯を支える骨に炎症が起こる病気で、気づかないうちにゆっくりと進行していくのが特徴です。
歯槽膿漏の正体と発症のメカニズム
歯槽膿漏は、歯周病の一種で、歯ぐきの炎症が進行して歯を支える骨(歯槽骨)が溶けてしまう状態を指します。原因の多くは、歯と歯ぐきの間に溜まった歯垢(プラーク)や歯石に含まれる細菌です。これらの細菌が長期間放置されると、歯ぐきが腫れたり、出血したりする炎症反応を引き起こします。
炎症が続くと、やがて歯ぐきの内部にある骨や靭帯にまで影響が及び、歯をしっかり支えられなくなっていきます。その結果、歯がぐらついたり、最悪の場合は抜け落ちてしまうこともあるのです。
初期段階では気づきにくいのが歯槽膿漏
歯槽膿漏は、初期のうちはほとんど痛みを感じないため、多くの方が発見を遅らせてしまいます。
例えば、歯ぐきの腫れや軽い出血があっても、「きつく磨いたからだろう」と自己判断してしまうケースが多いのです。
しかし、初期の炎症を放置すると、次第に歯ぐきの腫れが強くなり、歯の根元まで細菌が侵入します。やがて膿が出たり、口臭が強くなったりといった症状が現れ、気づいたときにはかなり進行していることも珍しくありません。
当院でも、「歯ぐきから血が出る」「口臭が気になる」といったきっかけで来院される患者様の多くが、検査をすると歯槽膿漏の初期〜中期に進行していることが分かるケースがあります。
歯槽膿漏が進行するとどうなる?
歯槽膿漏の進行は、大きく3つの段階に分けられます。
① 歯肉炎(初期段階)
歯ぐきのみに炎症があり、歯を支える骨にはまだ影響がありません。歯みがき時の出血や軽い腫れが見られます。適切なケアを行えば、この段階での回復は十分可能です。
② 軽度〜中等度の歯周炎
炎症が歯ぐきの奥へ広がり、歯を支える骨が少しずつ溶け始めます。歯ぐきが下がって歯が長く見えたり、冷たいものがしみたりすることがあります。
③ 重度の歯周炎(歯槽膿漏)
骨の吸収がさらに進み、歯が大きくぐらつくようになります。膿が出たり、噛むと痛みが出たりすることもあり、この段階では自然に治ることはほぼありません。
一度溶けた骨は自然に元に戻らないため、早期発見と早期治療が非常に重要です。
歯ぐきから血が出やすくなる生活習慣
歯槽膿漏のリスクを高める要因には、毎日の生活習慣が深く関係しています。
・磨き残しの多いブラッシング:歯垢が取りきれず、細菌が繁殖しやすい状態になる。
・喫煙:血流が悪くなり、歯ぐきの免疫力が低下する。
・ストレスや睡眠不足:体の抵抗力が落ち、炎症が悪化しやすくなる。
・糖尿病:血糖値のコントロールが難しいと、歯ぐきの治りも遅くなる。
・不適切な噛み合わせ:特定の歯に過度な力が加わり、歯ぐきへの負担が増える。
このように、歯槽膿漏は日々の生活と密接に関係しており、単なる「口の中の病気」ではなく、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
予防のために意識したいセルフケア
歯槽膿漏を防ぐためには、歯医者での治療と並行して、日々のセルフケアを徹底することが大切です。
特に以下の3つのポイントを意識すると良いでしょう。
・正しいブラッシング
歯ブラシは毛先の柔らかいものを使い、歯と歯ぐきの境目を優しく小刻みに磨くのがコツです。強く磨きすぎると歯ぐきを傷つけてしまうこともあるため注意が必要です。
・歯間清掃の習慣化
歯と歯の間は、歯ブラシだけでは汚れを落としきれません。歯間ブラシやデンタルフロスを併用し、細菌の温床を作らないようにしましょう。
・定期的な検診
3〜6か月に一度、歯医者でのクリーニングや検診を受けることで、早期の段階で異常を見つけることができます。
症状がなくても歯医者でのチェックを
歯槽膿漏は「痛みが出たときには進行している」病気です。
症状が軽いうちに気づくためには、定期的な歯科検診が欠かせません。
当院では、歯ぐきの状態を測る「歯周ポケット検査」や、歯を支える骨の状態を確認するレントゲン撮影を行い、目では見えない部分の炎症までしっかりチェックしています。こうした診断をもとに、一人ひとりの口腔環境に合わせたケア方法を提案しています。
歯ぐきからの出血を「たいしたことない」と放置せず、体からのサインとして受け止めることが、健康な歯を長く守る第一歩です。
歯医者で行う歯槽膿漏の治療と回復までの流れ
歯槽膿漏は一度かかると自然治癒が難しい病気ですが、適切な治療を行えば進行を止め、健康な状態を取り戻すことができます。ここでは、歯医者で行われる一般的な歯槽膿漏の治療法と、回復までの流れについて詳しく説明します。あおぞら歯科クリニック(当院)でも、患者様一人ひとりの症状や生活環境に合わせて段階的に治療を進めています。
歯槽膿漏の治療は「原因を取り除くこと」から始まる
歯槽膿漏の原因は、歯と歯ぐきの間にたまる**細菌のかたまり(プラークや歯石)**です。そのため、治療の第一歩は「細菌を減らすこと」。これにより、炎症を抑え、歯ぐきの腫れや出血を改善していきます。
・スケーリング(歯石除去)
初期〜中期の歯槽膿漏では、まずスケーリングと呼ばれる処置を行います。専用の器具を使い、歯の表面や歯ぐきの縁に付着した歯石を丁寧に取り除きます。歯石の表面はザラザラしており、細菌が付着しやすい環境を作り出します。これを除去することで、歯ぐきの炎症を抑えることができます。
スケーリング後は、数日〜数週間で歯ぐきの出血が減り、赤みや腫れが落ち着いてくる患者様が多く見られます。ただし、歯ぐきの奥(歯周ポケット)にまで汚れが入り込んでいる場合、さらに深い部分の治療が必要になります。
歯ぐきの奥に隠れた汚れを取る「ルートプレーニング」
歯槽膿漏が進行すると、歯と歯ぐきの間に「歯周ポケット」と呼ばれるすき間ができます。ここに細菌が入り込み、歯ぐきの奥で炎症を起こすのです。
このような状態では、表面のスケーリングだけでは不十分なため、ルートプレーニングという処置を行います。これは歯ぐきの内側にある歯根(歯の根っこ)の表面を滑らかにし、汚れや細菌を徹底的に除去する治療です。
この処置は、麻酔を使用して行うことが多く、痛みをほとんど感じずに受けることができます。ルートプレーニングを行うことで、細菌の再付着を防ぎ、歯ぐきが再び歯にしっかりとくっつくようになります。
治療後は、一時的に歯ぐきが引き締まったように見えることがありますが、これは炎症が落ち着いている証拠です。歯ぐきが健康なピンク色に戻り、出血が止まれば、症状は安定に向かっているといえます。
中等度〜重度の場合は外科的治療が必要になることも
炎症が長く続いている場合、歯ぐきの奥深くに歯石や膿がたまっていることがあります。その場合は、**フラップ手術(歯周外科手術)**という外科的な治療が行われることがあります。
フラップ手術では、歯ぐきを一時的に開いて、奥にこびりついた歯石や感染した組織を直接取り除きます。清潔な状態にしてから歯ぐきを元に戻すことで、炎症の再発を防ぐことができます。
また、失われた骨を回復させるために再生治療が行われる場合もあります。専用の薬剤や人工骨を使用して、骨や歯ぐきの再生を促す方法です。これは歯をできるだけ長く残すための重要な治療といえます。
ただし、すべての症例で再生が可能というわけではなく、骨の吸収状態や患者様の健康状態によって適応が異なります。
炎症を再発させないための「検診治療」
歯槽膿漏の治療で最も大切なのは、治療後の検診です。せっかく炎症を治しても、再び歯垢や歯石が溜まれば、歯槽膿漏は再発してしまいます。
当院では、治療後も1〜3ヶ月ごとの定期的な検診を推奨しています。専用の器具で歯ぐきの中までクリーニングを行い、家庭でのブラッシングでは落としきれない汚れを取り除きます。
また、歯科衛生士がブラッシング指導を行い、磨き方の癖や磨き残しやすい部分を一緒に確認します。こうした小さな積み重ねが、歯槽膿漏の再発を防ぐ鍵になります。
自宅でできる歯槽膿漏ケア
治療と並行して、自宅でのケアを見直すことも重要です。歯槽膿漏の改善を目指すために、次のようなポイントを意識しましょう。
・歯ブラシの選び方
柔らかめの毛先を選び、力を入れすぎずに小刻みに磨くことが大切です。毛先が開いてきたら早めに交換しましょう。
・歯間ブラシやデンタルフロスの使用
歯と歯の間は、歯ブラシだけでは汚れを落としきれません。歯間ブラシを使うことで、細菌のすみかを減らすことができます。
・舌の清掃と口臭ケア
舌の上にも細菌が付着するため、専用の舌ブラシで優しく清掃すると口内環境が整います。
・食生活の改善
ビタミンCやカルシウムを含む食品を積極的に摂り、歯ぐきの健康をサポートしましょう。糖分の摂りすぎは細菌の増殖を促すため注意が必要です。
・禁煙
タバコは血流を悪くし、歯ぐきの治りを遅くします。禁煙することで、歯槽膿漏の治療効果が高まりやすくなります。
全身の健康にもつながる歯槽膿漏治療
歯槽膿漏は口の中だけの問題ではなく、全身の健康にも影響を及ぼします。最近の研究では、歯周病菌が血流を通じて体内に入り込み、糖尿病・心臓病・脳梗塞・認知症などのリスクを高めることが報告されています。
つまり、歯ぐきの炎症を放置することは、全身の健康リスクを高めることにもつながるのです。
逆に、歯医者での治療と日常ケアを継続することで、体全体の健康を守ることにもつながります。
歯槽膿漏治療の期間と通院ペース
治療期間は、症状の進行度や患者様のケア状況によって異なります。
軽度であれば数回の通院で改善することもありますが、中等度〜重度では数ヶ月にわたる治療が必要になることがあります。
一般的な流れとしては、
①初診・検査(歯周ポケット測定、レントゲン撮影)
②スケーリング・ルートプレーニング
③再評価(治療効果の確認)
④必要に応じて外科的治療
⑤定期検診
というステップで進んでいきます。
歯槽膿漏の改善には、歯医者での治療だけでなく、日々のケアを継続する意識が欠かせません。歯ぐきの健康を保つことは、見た目の美しさだけでなく、食事を楽しみ、体の健康を維持するための基盤になります。
まとめ
今回は、歯ぐきからの出血と歯槽膿漏の原因、そして歯医者で行う治療の流れについて説明しました。
歯槽膿漏は、歯ぐきや骨の炎症によって歯を支える力が弱まり、放置すると歯が抜けてしまうこともある病気です。早期の段階であれば、歯石除去や歯ぐきのケアによって改善が可能であり、日々のブラッシングや定期的なメンテナンスが何より大切です。歯ぐきからの出血や口臭、歯のぐらつきなど、気になる症状がある場合は、早めの受診が健康を守る第一歩となります。
あおぞら歯科クリニック本院では、歯槽膿漏に関するご相談を随時実施しておりますので、ぜひご相談ください。
この記事の編集担当は古橋淳一歯科医師です。

